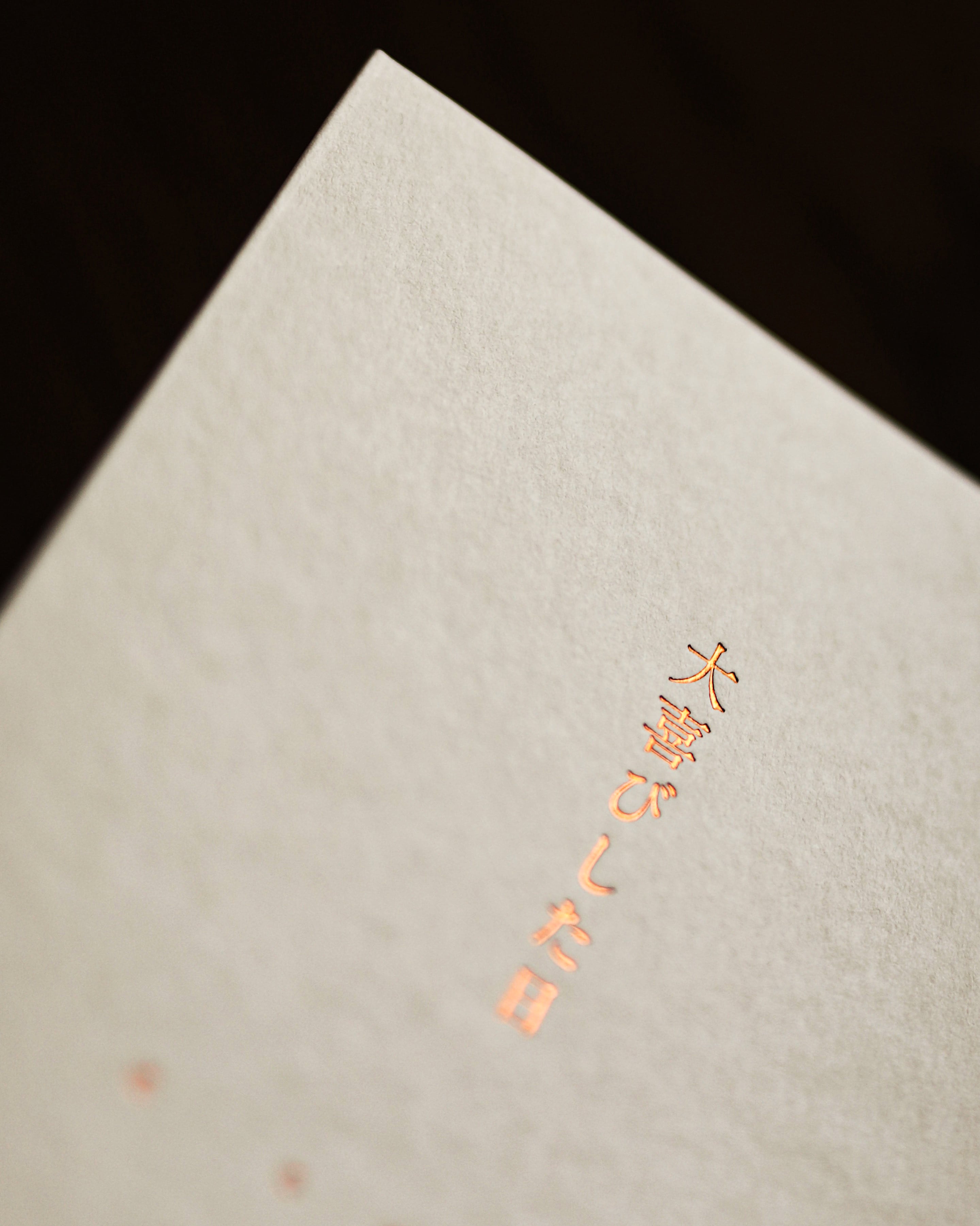『休み時間の過ごし方 地方公立中学校における文化とアイデンティティをめぐるエスノグラフィー』
¥2,420
『休み時間の過ごし方 地方公立中学校における文化とアイデンティティをめぐるエスノグラフィー』團康晃、烽火書房フリントブックス
2025年2月発行、4月発売、2200円(+税)、並製本324ページ、四六判
文化とアイデンティティが織りなす休み時間へ。
「調査者」として地方公立中学校に通い、生徒たちとともに日々を過ごした著者によるエスノグラフィー。
何気なく学校に居ること、特に授業ではなくその隙間である休憩時間、「休み時間」の経験がいかなるものなのか調査することを通して、学校に居ることの意味を問い、外の文化が学校の内側にどう持ち込まれているのか、学校の中でどのように文化やアイデンティティが育まれているかを明らかにする一冊。
学校という制度が人びとにもたらしている多種多様な経験の中で、これまで光をあてられてこなかった休み時間に光をあてる。
著者が2020年に東京大学大学院学際情報学府に提出した博士論文(『休み時間の社会学:相互行為、成員性、メディア』)をもとに、著者がどのようにフィールドに入り、生徒たちと関係性を築きながら休み時間を研究していったのかを辿る「体験記」として再構成。学校現場に携わる関係者だけでなく、学校という場所に関心がある人、研究アプローチに関心がある人へも薦めたい一冊。
(大阪経済大学研究叢書98冊)
もくじ
0.はじめに
第1部 「休み時間の過ごし方」の発見
第1章 「休み時間の過ごし方」という主題
1-1.「共に在ること」:公共空間としての休み時間
1-2.「グループとなること」:その図式があることと、その当事者になること
1-3.「道具が用いられるということ」:アジールとしての本、バトンとしての本
1-4.本書の主題
メモ1「休み時間」とは何か
第2章 フィールドの背景と調査の過程
2-1.中学校をフィールドとすること
2-2.渚中学校について
2-3.中学生の一日の流れ
2-4.調査に入るまで
2-5.調査の内容について
2-6.学校の中の調査者
メモ2 教室とクラスとHR
第3章 学校に集まる人びとへの幾つかの関心:先行研究について
3-1.「学級経営論」「集団づくり論」と「教育社会学」
3-2.生徒を類型化する:生徒文化研究の展開
3-3.若者文化の流入する場としての学校:「生徒文化研究」のその後
3-4.日本におけるサブカルチャーグループエスノグラフィーの展開
メモ3:「授業時間」と「休み時間」
第4章 「休み時間の過ごし方」を見る方法
4-1.グループインタビューのための「グループ」作りをめぐって
4-2.学校という社会の中でインタビューに答えるということ
4-3.カーストとしていくつかの「グループ」を描く
4-4.カーストとして「グループ」を描かない
4-5.「インタビュー」を「からかい」に変える
4-6.調査者による「グループ」の設定ではなくメンバーによる「成員性」の観察へ
4-7.常に適切なカテゴリーと共成員性
メモ4:学校に持ち込まれる「モノ」、持ち込まれる「アイデンティティ」
第2部 「休み時間の過ごし方」の探究
5章:学校の中でケータイ小説を読むこと
5-1.学校の中の「読者」へのアプローチ
5-2.ケータイ小説の「読者」であることをめぐって
5-3.ケータイ小説読者としての「女子」:作品を通した恋愛語り
5-4.ケータイ小説と「男子」:「エロ」いものとしてのケータイ小説
5-5.例外的な男子のケータイ小説読者
5-6.まとめ
メモ5:「アイデンティティ」を「見せること」
第6章:学校の中で物語を編むことについて
6-1.物語が書かれたノートとの出会い
6-2.「オタク」であることと校内放送
6-3.教室の中で物語を書くこと
6-4.共同で大学ノートに物語を書くこと
6-5.大学ノートをきっかけに廊下に集うこと
6-6.廊下に集うことへのまなざしと、それでも廊下に集まり続けること
6-7.まとめ
メモ6:「ヘテロトピア」としての「休み時間」
第7章:学校の中で「リーダー」になれること、「凡人」であること。
7-1.「リーダーになれる」:専門委員会委員長立候補をめぐって
7-2.「俺は凡人だから」:委員会立候補期間の終わり
7-3.「生徒会」のパロディとしてのピロティでの「あいさつ運動」
7-4.「革命的」あいさつ運動の終わり
メモ7:「休み時間」と「余暇」
第8章:本編の終わりに
第3部 学校現場におけるメディア環境を知るための補論
第9章【補論1】:学校の中の書籍とメディアミックスについて
9-1.学校の中に持ち込まれるモノをめぐって
9-2.学校読書調査の二次分析:メディアミックス系書籍が支持される実態
9-3.終わりに
第10章【補論2】:当時、渚中学校ではどんな本がどのようにして読まれていたのか
10-1.渚中学校の学校図書館
10-2.渚中学校における学級文庫について
10-3.渚中学校における朝の読書運動について
10-4.ケータイ小説読者について
第11章【補論3】:渚中学校における文化受容について
11-1.中学生のコンテンツ受容について:アンケート調査の結果から
11-2.中学生になる中での遊びの変化について:インタビュー調査の結
果から
あとがき
参考文献
-
装丁 小林誠太(seee)
装画・挿画 もんくみこ
印刷 シナノ書籍印刷
2025年2月発行、4月発売、2200円(+税)、並製本324ページ、四六判
文化とアイデンティティが織りなす休み時間へ。
「調査者」として地方公立中学校に通い、生徒たちとともに日々を過ごした著者によるエスノグラフィー。
何気なく学校に居ること、特に授業ではなくその隙間である休憩時間、「休み時間」の経験がいかなるものなのか調査することを通して、学校に居ることの意味を問い、外の文化が学校の内側にどう持ち込まれているのか、学校の中でどのように文化やアイデンティティが育まれているかを明らかにする一冊。
学校という制度が人びとにもたらしている多種多様な経験の中で、これまで光をあてられてこなかった休み時間に光をあてる。
著者が2020年に東京大学大学院学際情報学府に提出した博士論文(『休み時間の社会学:相互行為、成員性、メディア』)をもとに、著者がどのようにフィールドに入り、生徒たちと関係性を築きながら休み時間を研究していったのかを辿る「体験記」として再構成。学校現場に携わる関係者だけでなく、学校という場所に関心がある人、研究アプローチに関心がある人へも薦めたい一冊。
(大阪経済大学研究叢書98冊)
もくじ
0.はじめに
第1部 「休み時間の過ごし方」の発見
第1章 「休み時間の過ごし方」という主題
1-1.「共に在ること」:公共空間としての休み時間
1-2.「グループとなること」:その図式があることと、その当事者になること
1-3.「道具が用いられるということ」:アジールとしての本、バトンとしての本
1-4.本書の主題
メモ1「休み時間」とは何か
第2章 フィールドの背景と調査の過程
2-1.中学校をフィールドとすること
2-2.渚中学校について
2-3.中学生の一日の流れ
2-4.調査に入るまで
2-5.調査の内容について
2-6.学校の中の調査者
メモ2 教室とクラスとHR
第3章 学校に集まる人びとへの幾つかの関心:先行研究について
3-1.「学級経営論」「集団づくり論」と「教育社会学」
3-2.生徒を類型化する:生徒文化研究の展開
3-3.若者文化の流入する場としての学校:「生徒文化研究」のその後
3-4.日本におけるサブカルチャーグループエスノグラフィーの展開
メモ3:「授業時間」と「休み時間」
第4章 「休み時間の過ごし方」を見る方法
4-1.グループインタビューのための「グループ」作りをめぐって
4-2.学校という社会の中でインタビューに答えるということ
4-3.カーストとしていくつかの「グループ」を描く
4-4.カーストとして「グループ」を描かない
4-5.「インタビュー」を「からかい」に変える
4-6.調査者による「グループ」の設定ではなくメンバーによる「成員性」の観察へ
4-7.常に適切なカテゴリーと共成員性
メモ4:学校に持ち込まれる「モノ」、持ち込まれる「アイデンティティ」
第2部 「休み時間の過ごし方」の探究
5章:学校の中でケータイ小説を読むこと
5-1.学校の中の「読者」へのアプローチ
5-2.ケータイ小説の「読者」であることをめぐって
5-3.ケータイ小説読者としての「女子」:作品を通した恋愛語り
5-4.ケータイ小説と「男子」:「エロ」いものとしてのケータイ小説
5-5.例外的な男子のケータイ小説読者
5-6.まとめ
メモ5:「アイデンティティ」を「見せること」
第6章:学校の中で物語を編むことについて
6-1.物語が書かれたノートとの出会い
6-2.「オタク」であることと校内放送
6-3.教室の中で物語を書くこと
6-4.共同で大学ノートに物語を書くこと
6-5.大学ノートをきっかけに廊下に集うこと
6-6.廊下に集うことへのまなざしと、それでも廊下に集まり続けること
6-7.まとめ
メモ6:「ヘテロトピア」としての「休み時間」
第7章:学校の中で「リーダー」になれること、「凡人」であること。
7-1.「リーダーになれる」:専門委員会委員長立候補をめぐって
7-2.「俺は凡人だから」:委員会立候補期間の終わり
7-3.「生徒会」のパロディとしてのピロティでの「あいさつ運動」
7-4.「革命的」あいさつ運動の終わり
メモ7:「休み時間」と「余暇」
第8章:本編の終わりに
第3部 学校現場におけるメディア環境を知るための補論
第9章【補論1】:学校の中の書籍とメディアミックスについて
9-1.学校の中に持ち込まれるモノをめぐって
9-2.学校読書調査の二次分析:メディアミックス系書籍が支持される実態
9-3.終わりに
第10章【補論2】:当時、渚中学校ではどんな本がどのようにして読まれていたのか
10-1.渚中学校の学校図書館
10-2.渚中学校における学級文庫について
10-3.渚中学校における朝の読書運動について
10-4.ケータイ小説読者について
第11章【補論3】:渚中学校における文化受容について
11-1.中学生のコンテンツ受容について:アンケート調査の結果から
11-2.中学生になる中での遊びの変化について:インタビュー調査の結
果から
あとがき
参考文献
-
装丁 小林誠太(seee)
装画・挿画 もんくみこ
印刷 シナノ書籍印刷